キーワードで探す
多目的トイレ、クリスマスイヴ
きのコ
公開日|2022.08.04
更新日|2022.08.04
《セックスしたいです》
「…ってLINEが来たんだけど。今」
「はぁ」
私が差し出したスマホの画面を覗きこんでいたアキが、眉根を寄せて顔をあげる。
「どうするん」
「……さぁ」
私はスマホを置いて、食後のコーヒーのカップを手に取った。私とアキの昼休みが終わるまで、あと15分。会社に近いこのカフェレストランでのランチが私たちの日課だ。
「ケンさんだっけ?元カレっていうか、セフレっていうか」
「まぁ、それ」
「もう切るって言ってたけどまだ続いてたんだ。会うの?」
「イヴは休みで暇だってさ」
「てことは」
「……さぁ」
カップを持ったまま、私は呟いた。
「まぁ私は仕事だし、ないでしょ、イヴなのにセフレと会うとか」
それが10日前。
駅前に設置された大きなツリーの前に、彼は立っていた。ポケットに手を入れたまま近づく。プレゼント用のラッピングに包まれたキーリングを、ポケットの中の指先で確かめる。
「お疲れさまです」
「お疲れさまです」
何度セックスしても、どうしても敬語を崩せないのが私達の距離感だ。なのにどうして、定時退社してまで会いに来てしまうのだろう。年末は繁忙期で残業続きなのに。
「行きますか」
「はい」
無言で歩く背が高い彼の大股に、いつもより気持ち速足で合わせる。合わせてしまう。いつだってそうだ。
口元まで覆ったマフラーの中で、聞こえないように溜息をついた。
パステルオレンジの塀に囲まれた建物の入口に、「満室」のサインが赤く灯っている。まだ20時だというのに、3軒目のラブホテルも満室だった。これがイヴか。
「空いてないですね。ちょっと散歩しますか」
…さんぽ?
定期的に会っていても、私達は食事もしない。ディズニーランドにも行かない。クリスマスプレゼントを贈りあうわけでもない。散歩?
よく分からないまま彼についていく。ついていってしまう。通りはイルミネーションがさざめいて、昼よりなお明るい。
「ここです」
彼が入口をくぐったのはなんとかヒルズ。の、フロアの片隅から非常階段を降りていく。エレベーターもエスカレーターもカップルで混雑しているけど、さすがに階段を使う人はいない。
降り立った地下駐車場にはベンツか何かの高級車がずらりと停まっているが、ここにも人の気配はほとんどない。柱の陰にある扉を彼が開ける。
「…多目的トイレですよね。ここ」
「入ってください、人が来ますよ」
彼が私の腕をとって個室の中へ引き込む。道を歩く時には手も繋がないのに。
ドアに鍵を掛ける彼をぼんやり見る。彼といるといつも、大事なことがあったのに思い出せなくなるような気がする。今日はイヴで、ラブホテルが空いてなくて、ここは多目的トイレで、つまり、
「…っ」
振り向きざま引き寄せられ、何も言わず唇を重ねられて、思考が止まる。そのまま彼の手が私の尻に回り、スカートをたくし上げ、太腿の付け根に指が食い込んでくる。
「ひっ、」
突然爪を立てられて、唇を塞がれたまま喉で声を立ててしまう。同時に、かっ、と体が熱くなる。彼の指先はこんなに冷たいのに。いつだってそうだ。
彼の手に力がこもるほど、私の手からは力が抜けて、持ったままだったハンドバッグを床に取り落としてしまう。ぼふん、と音がした。
彼は左手で私の尻をわしづかみにしたまま、右手で私の背をなぞり上げ、後ろで束ねていた髪の根元を掴んだ。ぐっと圧がかかって、頭皮が引き攣れる。あ、あ、という自分の声が遠くに聞こえ、目元に涙が滲んだ。
きつく閉じていた目を開ける。彼の顔は近すぎてぼやけているが、目が合ったことは分かった。途端、
「!!ぁがっ!」
舌を噛まれて、口を閉じることも振りほどくこともできず、私はくぐもった悲鳴をあげて硬直する。太腿に爪を立てられる痛み、髪を捩じりあげられる痛み、舌を噛まれる痛み、それぞれが錯綜して体の芯がぐずぐずに溶け崩れるようだ。
彼の左手の指が、尻の割れ目をなぞってショーツの脇から侵入してきた。
「んぅ!」
躊躇なく中指を突き込まれて、背中が反りかえる。指を冷たく感じるのは、裏返せば私の身体がそれだけ熱を帯びているということだろう。
髪を掴む右手は緩めず、彼が耳元で言う。
「とろとろになってますね。いつも最初から」
羞恥と悔しさで思わず目をそらす。頬に血がのぼる音が聞こえたような気がした。たぶん、ツリーの下にいる彼を見た瞬間から、濡れ始めて、濡れ続けている。
彼はようやく両手を離すと、当たり前のような手つきでジーンズを下ろして、
「後ろを向いてください」
と当たり前のような口調で言った。
あぁ。いつだってそうだ。
彼に私への恋愛感情がないことは分かっている。私に彼への恋愛感情があることも。
何度会っても、心は1mmも近づけない、体しか交わらない。けれど、それだけでもあるなら、それさえもないよりはいい。…と、思っているわけじゃないけど。
私は黙って壁の方を振り向いた。冷たい壁に両手を這わせる。
彼が無言で私の腰を掴んだ。勃起の先端で、わざと太腿の内側をゆっくり撫であげてくる。
濡れそぼった割れ目を竿の胴で前後にこすられると、後からあとから蜜が溢れ出してきてしまう。彼は壺の入口に先端をあてがうと、左手を私の口に、右手を私の喉元に当てた。相変わらず冷たい指先。
「ぅぐっ!!」
馴らしもせず、彼がひと思いに最深部まで叩きこんでくる。同時に両手それぞれに力を込められて、喉がぐっと絞られ、声が出せない。
彼の手は冷たいのに、私を貫く肉棒だけがたぎるように熱い。それを感じて、自分の体温がまた1度あがった。目の前の壁が霞んで見える。
イヴの夜、狭くて寒い多目的トイレの中で、服も着たまま秘所を蹂躙されながら、私は大粒の涙をぼたぼた零している。悲しいのか、嬉しいのか、苦しいのか、気持ちいいのかも、もう分からない。嗚咽を上げたくても、声すら出させてもらえない。彼の槍だけがますます熱くなり、私の中も蜜を煮詰めたように熱を帯びていく。
彼のピストンがひときわ激しくなった。首を絞められ口を塞がれて、私の視界は白く歪んでいる。白から灰色、灰色から黒へと暗くなって、暗転するかという一瞬、彼が思いきり奥まで突きこんで静止した。熱い、重いどろりとしたものが膣の奥に叩きつけられる感触が伝わってくる。
やっと手を緩められて、私は身を折って咳きこんだ。涙と涎と鼻水が混じりあって、顔はぐしゃぐしゃになっていることだろう。
布が擦れる音、金属が触れあう音がして顔をあげた。彼がジーンズを引きあげ、ジッパーを閉めてベルトを締めなおしている。
手早く身づくろいを済ませると、彼はまだ壁にもたれて息をはずませている私に顔を向けた。
「一緒に出て誰かに見られるとまずいので、先に出ますね。それじゃ」
言うなり、素早くドアが開かれて、素早く後ろ手に閉まる。
「……ぁ」
靴音が遠ざかって、消える。
何かを言おうとして、何も言えないまま、私は寒々とした箱の中に取り残された。
そのまま数分間、痛みと疲労感で、茫然と壁に手をついていたと思う。
床に落ちたままだったハンドバッグの中から、ぴこぴこ、と電子音がして私は我に返った。緩慢な動きでバッグを拾い上げ、スマホを取り出す。
《結局会ったのー?せっかくのイヴなのに時間の無駄じゃん!って、私もいま残業終わったんだけど、このあと何もないし飲まない??》
アキの、いつもの口調そのままのLINEと絶妙に可愛くないゆるキャラのスタンプに、ずっとこわばっていた体が少しだけ緩んだ気がした。
ようやく体をきちんと起こして、洗面台で手を洗う。ついでに顔も洗ってしまう。水は冷たいけど、彼の指ほどじゃない。
トイレットペーパーをわざと大量に引っ張り出して、冷えた股間を手早く拭いて、便器に投げこんで勢いよく流してしまう。気持ちとか、そういういろいろも含めて。
掴まれて乱れた髪を撫でつけてから、アキに《じゃあいつものカフェレストランね!》と返信する。そのまま、あーぁ、と声に出して、その言葉で自分を後押しするように、彼のLINEの連絡先を削除した。
背を伸ばしてポケットにスマホを入れた時、指先にリボンをかけた包みが触れた。そうだった。
取り出して手の平にのせる。渡していたら、渡せていたら、何か変わったんだろうか。
「…そんなわけないか」
呟いて、トイレのゴミ箱にプレゼントを押し込んだ。ちょっと勢いよくドアを開ける。
彼に合わせるためでなく自分のために、いつもより大股で、私はエレベーターへ歩き出した。
.gif)
もっと読みたい!あなたにおすすめの記事はこちら

ログインをすると利用出来ます

きのコ
の他の投稿
関連する体験談
関連するコラム

セフレ

セフレ

セフレ










.ai (1).png)

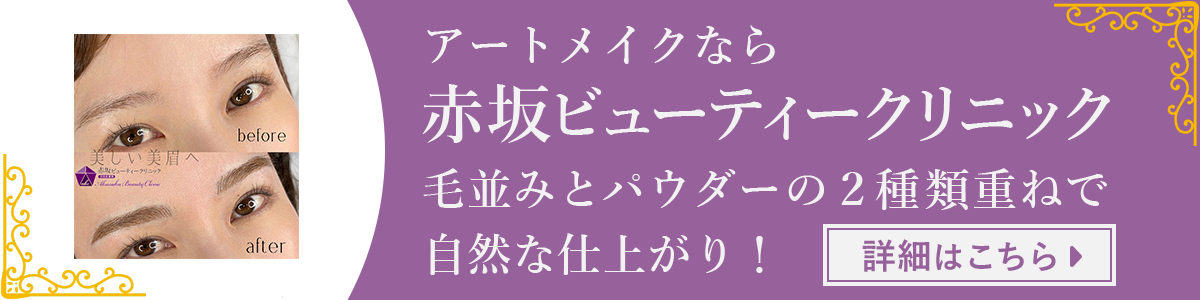
.ai.png)
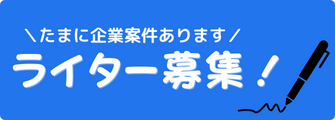
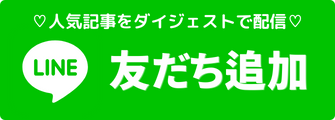




コメントを書く